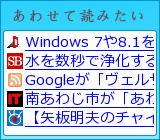さよなら妖精 - 著者: 米澤穂信
著者: 米澤穂信
紹介
別にどこにでもいるような高校生・守屋路行は、友人の大刀洗万智と下校途中、ちょっと路を外れたために、雨宿りしている一人の少女と出会った。やや片言な日本語を操る、ユーゴスラヴィアから来たマーヤに。
1991年4月23日。
僅か二ヶ月というホームステイの間に、彼女は貪欲に日本のことを知りたがった。
「哲学的意味がありますか――?」
守屋、万智、そして奇妙な成り行きから彼女のステイ先になった白川いずる、守屋の部活仲間文原たちとの交流と、そして別れ。
1991年6月。ユーゴ内戦が始まっていた。
青春の甘さと酸っぱさに謎掛けが加わる米澤穂信の作品の中では、酸味がきつい作品です。
1991年の春から夏にかけての、国を越えた青春交流から、時々に挿入される1992年の情景。読者は自分の知識にある“あの”ユーゴ内戦の光景を思い出しながら、登場人物たちと同じようにマーヤの故郷がユーゴのどこなのかどうしても気に掛かります。
あの日の僕達に、その国は余りにも遠すぎて――。
そんなフレーズを思い付いてしまう、切ないお話です。
コメント
- 2007-09-24 (Mon) 02:23:31 S.B. : ユリイカ2007年4月号に掲載された「失礼、お見苦しいところを」に、大人になった守屋と万智が登場しています。
- 2006-08-20 (Sun) 16:44:31 きさら : 文庫版読了。素晴しい。個人的に多少旧ユーゴ諸国に縁があり思い入れもあるのですが、酸味のきつい作品ですね。
- 2006-06-17 (Sat) 21:25:35 きさら : フランス装幀版と文庫版では、一部セリフが変わっている箇所があるそうです。
- 2006-06-13 (Tue) 20:33:22 S.B. : お求めやすい価格の文庫版が出ました。この機会に是非ご一読を!
既刊
関連項目
- 遠まわりする雛 - 著者: 米澤穂信
- 犬はどこだ - 著者: 米澤穂信
- 氷菓 - 著者: 米澤穂信
- 春期限定いちごタルト事件 - 著者: 米澤穂信
- 愚者のエンドロール - 著者: 米澤穂信
- ボトルネック - 著者: 米澤穂信
- クドリャフカの順番 - 著者: 米澤穂信
- インシテミル - 著者: 米澤穂信
- うれしの荘片恋ものがたり - 著者: 岩久勝昭
- ようこそ無目的室へ! - 著者: 在原竹広
- 富士見ミステリー文庫 - 富士見書房
- 売り上げランキング(2019-......
- 売り上げランキング(2018-......
- 売り上げランキング(2017-......
- 売り上げランキング(2016-......
- 売り上げランキング(2015-......
- 売り上げランキング(2014-......
- 売り上げランキング(2013-......
- 売り上げランキング(2012-......
- 売り上げランキング(2011-......
- 売り上げランキング(2010-......
- 売り上げランキング(2009-......
- 売り上げランキング(2008-......
- 売り上げランキング(2007-......
- 米澤穂信 - よねざわ・ほのぶ
- 既刊情報(2002年) - 2002年の既刊情報
- 既刊情報(2001年) - 2001年の既刊情報
 さよなら妖精
さよなら妖精 さよなら妖精
さよなら妖精